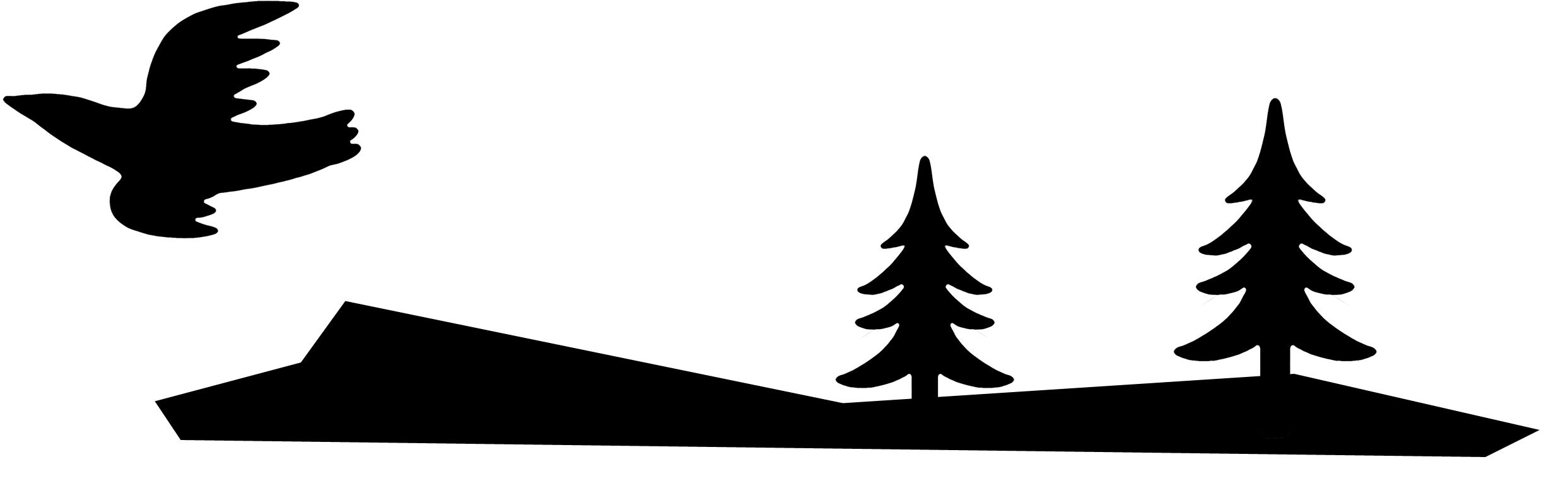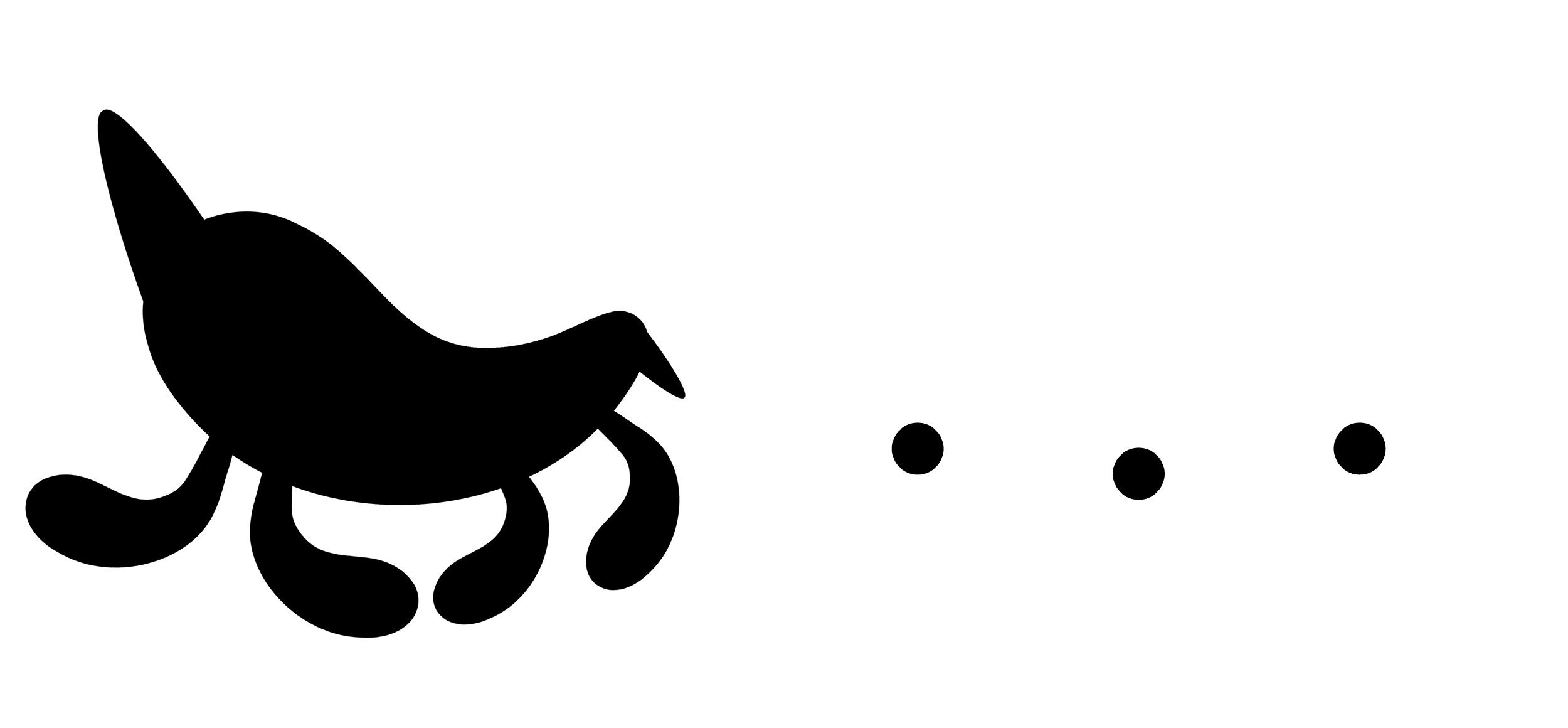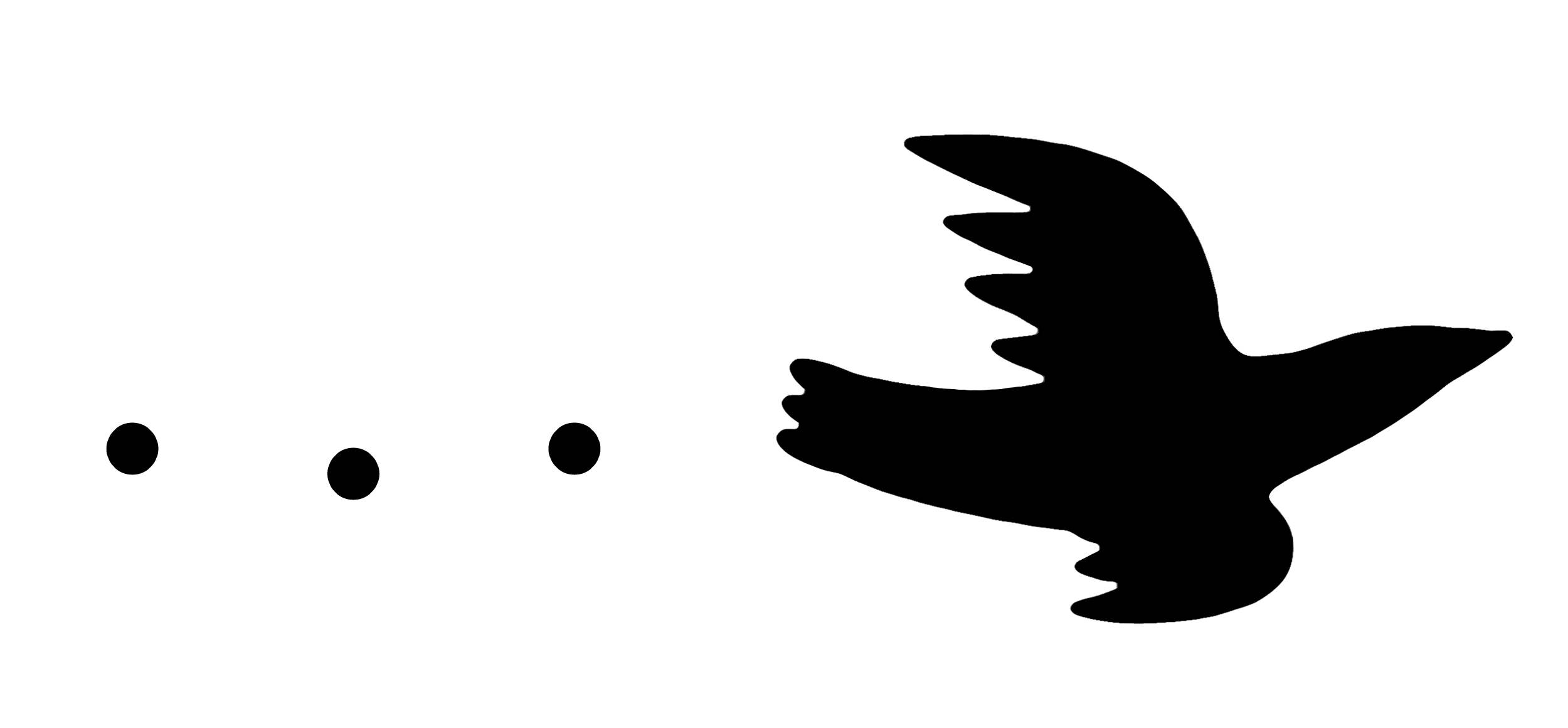4月7日のことです、空から魔法の粒が森の地面に降り注ぎました。
魔法といっても、それは難しいものではありません……森はいつでも、不思議に美しいもので満ち溢れているのです。

ともかく、そのキラキラとした粒のお陰で、森の野原では長い冬の間じゅう暗い土の中でぐっすりと眠っていたカエルたちが一斉に目を覚ましました。 そして、その日の夕暮れには太陽が傾くと同時にほんのりと湿った風が心地良く流れ始め、カエルたちはそれぞれ思い思いに、しかし皆一斉に歌い出したのです。
長い長い冬、暗く音の無い穴の中でじっと時を過ごしていた生き物たちにやっと春が来たのですから、それはもう、彼らが大声で歌い出したくなるのは無理もありません。
そうして、それまでの日々冷たく静かだった森が、新しい命を紡ぐための歌、美しい恋の歌で満ち溢れました。

(嗚呼、金色の陽射しに照らされながら、皆が一緒に歌っている……なんて素晴らしい光景だろう。これはまさに、寒い冬の土の中で何度も夢見た温かい春、そのものだ。)
一匹のカエルが、これから始まるであろう美しい季節に想いを馳せ、心を躍らせました。
(よし、僕も歌うぞ。)
しかし、ちょうどその時です、草むらの仄暗い隙間から小さな声が聞こえました。
『これも、夢なのかもしれませんね……』
それは、大合唱の中にあってなお、透き通るような、光るような不思議な声でした。

その姿は見えませんでしたが、それはいつか遠い昔に聴いたことのある懐かしい声でしたので、カエルは嬉しくなってこう答えました。
『夢というのは暗い冬穴の中で見るものではありませんか、それなら僕はもう751回も春の夢を見ました。けれど、これは夢なんかではなく本物の春です、この僕だって今すぐに美しく歌ってみせますよ。』
そうして、誇らしげに歌い始めたのです。

『そうですね、どちらでも好いことなのかもしれません……光と影のように、いずれも等しく繋がっているのですから……世界の表と裏、あるいは、失うことと得ること、生きることと死ぬことでさえ、また同じなのかもしれませんね……』
その透き通った声は、やがて微かに消え入りました……もう誰の耳にも届きません。
野原にはカエルの声だけが響き渡り、やがて丸い月が顔を出すと、森のあちこちで小さな命が生まれ始めたのでした。

朗読はこちら